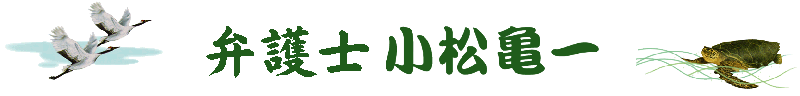○Cの妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料500万円と弁護士費用・調査費用等合計824万円の支払を求めました。
○被告は、Cはほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化し、被告と関係を持つ以前に、D女と関係を持つなどして、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻しており、また、調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められないと争いました。
○これに対し、CとD女とは相当程度親密と認められるが態様・期間等の明確な証拠がなく、Cの言動は、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると評価できず、被告が、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえるとして慰謝料100万円と弁護士費用10万円の支払を命じた令和6年11月22日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。
○調査費用については、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあり、その調査が必要不可欠で本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いとして請求を棄却しました。
○別居等明確な破綻状況がないと貞操義務を否認する婚姻破綻は認めないのが判例の一般的傾向で、この判例もそれに従っています。興信所等調査費用も一般的には認めないのが判例の傾向でそれに従っています。
*********************************************
主 文
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の、その余を被告の各負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、824万4546円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、C(以下「C」という。)の妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料等及び遅延損害金(起算日は訴状送達日の翌日である令和5年5月21日)の支払を求める事案である。
1 前提事実
以下の事実は、当事者間に争いがないか、証拠上容易に認めることができる(なお、枝番号の記載は省略する。)。
(1)原告とCは、平成20年に婚姻した夫婦であり、両者の間には、平成24年生まれの長男と、平成29年生まれの長女がいる。
(2)被告は、遅くとも令和元年12月末から令和3年2月頃までの間、Cと性関係を伴う交際をしていた。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は、〔1〕婚姻関係破綻の有無、及び、〔2〕損害額であるところ、これらの争点に関する当事者の主張は次のとおりである。
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
(被告の主張)
Cは原告を顧みることなく、ほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化していた。また、Cは被告と関係を持つ以前に、D(以下「D」という。)という女性と関係を持つなどしており、これらのことなどから、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻していた。
(原告の主張)
原告とCは継続して同居しており、その夫婦関係は円満である。また、DとCとの不貞関係の有無は不明であり、少なくとも原告にそれが発覚したなどの事情はなかったのであるから、婚姻関係は被告がCと関係を持った時点で破綻していなかった。
(2)争点〔2〕(損害額)について
(原告の主張)
慰謝料 500万円
弁護士費用 50万円
不貞行為の調査費用 274万4546円
合計額 824万4546円
(被告の主張)
否認ないし争う。調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
上記第2の1前提事実に加え、証拠(乙27、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)被告は、令和元年9月頃、勤務していたクラブにおいて、客として訪れたCと知合い、同年12月29日頃に性交渉を持ち、令和2年1月頃にクラブを退職し、Cから生活費の援助を受けながら、継続的に交際するようになった(甲2)。
(2)原告は、代理人弁護士を介して、令和2年4月24日到達の書面で、被告がCと不貞行為に及んでいるとして、被告に対し、慰謝料300万円を支払い、Cとの交際を止め、原告に謝罪するよう求めた(甲3)。
その後、原告の当時の代理人と被告は電話で話をしたが、慰謝料の支払や交際の中止には至らなかった(甲4,5)。
(3)被告とCが、令和2年5月20日、千葉県のゴルフ場にいたところ、原告がその場に現れ、被告に、Cと別れるよう求めた。
(4)Cは、令和2年8月14日、東京都港区αのマンションを賃借した。その契約書では、居住者はCと被告の2名とされ、被告の続柄は「婚約者」とされていた(乙8)。被告は、それ以降、令和3年6月頃まで同所に居住しており、Cがそこを訪れ宿泊することもあった。
(5)Cと被告は、令和2年11月頃から、関係に不和が生じ、令和3年2月頃に最後の性関係を持った。被告は、Cから退去を求められたことから、同年6月頃、上記αのマンションを退去した。
(6)Cは、自らが代表取締役を務めるa株式会社の本店住所を令和2年9月まで東京都港区β(以下省略)としていたが、同所は、平成2年生まれの女性であるDの平成30年4月から令和2年5月までの住民票上の住所と同じであった(乙4,5)。
また、原告は、時期は不明であるが、Cの携帯電話を用いて、Dに対し、「妻です。夫と別れてください」というメッセージを送ったことがあった。
(7)原告とCは、Cのクリニックの診療等のため、平日に夕食を一緒に取ることは乏しかったが、Cが、原告が居住する自宅で過ごすこともあり、原告及び子らと共に家族旅行に行くなどしていた(甲13)。
なお、この点について、被告は、Cが原告と別居していたと主張しており、たしかに、Cは、Dが居住していたa株式会社の本店住所や、被告を居住者として賃借した建物などで、一定の時間を過ごすことがあったことは窺えるものの、それを超えて、原告が居住する自宅に帰らずに別居していたことまでを認めるに足りる証拠はない。
(8)原告は、令和2年3月に、探偵業社にCの行動調査を依頼し、同月5日から同年4月14日までの間の調査料金として、同月21日に249万4546を支払った(甲7)。
2 争点に対する判断
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
上記認定事実記載のとおり、原告とCは、被告がCとの性関係を持ち始めた令和元年12月末の時点で同居を継続しており,特段の明示的な不和は認められない。
また、CとDの関係については、Cが代表を務める会社の住所にDが居住していたことや、原告もCとDとの間で、不貞を疑うようなやりとりを発見したから、Dに対して別れることを求めるメッセージを送ったと思われることなどからすると、CとDとの間で、相当程度の親密な関係があったことは窺えるものの、その態様や期間等については、明確に裏付けるまでの証拠はなく、また、仮にCとDとの間で不貞関係が存在していたとしても、それが原告に発覚したことで、原告とCが別居に至るなど、夫婦関係に何らかの顕著な悪化が生じた事実も認められない。そして、Cが、D以外の女性と不貞を行っていたことを認めるに足りる証拠もない。
そうすると、原告とCの婚姻関係が、令和元年12月末の時点で、破綻に至っていたとはいえない。
そして、被告の認識について検討するに、たしかに、Cは、被告に対して「心の底から愛してる」と言う一方で、原告について「こんな人と結婚しちゃった」などと不服を伝えるなどしており(乙10)、さらに、賃貸借契約を締結するにあたって、被告を「婚約者」としているなどの事実は認められるものの、これらは、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると考えるに足るものとまでは評価できない。
したがって、この点の被告の主張は理由がなく、被告が、令和元年12月末以降、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえる。
(2)争点〔2〕(損害額)について
ア 本件に現れた一切の事情、特に、被告とCの交際期間が約1年強に及び、その間継続的に性関係があったことが窺えること、原告からCとの交際を辞めるよう求められたにも関わらず、関係の継続に至っていること、他方で、Cには、原告としても不貞を疑うような別の女性とのやりとりがみられたこと、原告とCは離婚には至っていないことなどの事情を踏まえれば、本件の慰謝料は100万円と認めるのが相当であり、本件と相当因果関係のある弁護士費用は10万円と認められる。
イ 原告が負担した調査費用については、上記のとおり、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあったことなどからすれば、その調査が必要不可欠であり、その費用が本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いから、この点の損害は認められない。
3 結論
以上の次第で、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事26部 裁判官 堂英洋
以上:3,968文字
Page Top