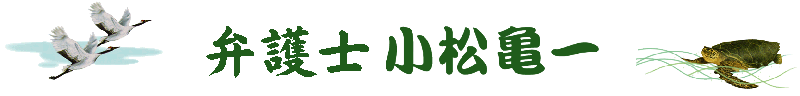○横浜パートナー法律事務所
代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年2月1日発行第406号「
弁護士の「嘘つき!」」をお届けします。
○大山先生は、ChatGPTを良く利用されるとのことですが、私はグーグルAIを良く利用します。確かに結構便利ですね。同じ質問をChatGPTとグーグルAI両方にしてみるとほぼ同じような回答が返ります。
○最近、訴訟中のお客様から、訴訟での問題点についてChatGPTで確認した内容をメール送付されてきた方が居ました。これからはそのような方が増えるかも知れませんので、私も度々利用するようになりました。法律上の問題点だけでなく、健康上の問題や、趣味の映画での疑問点など全ての問題について、万遍なく回答してくれます。法律上の問題点は、グーグルAIでは、最後に「
弁護士などの専門家に相談して手続きを進める必要があります。」、「
AIの回答には間違いが含まれている場合があります。」と述べて良心的です。ChatGPTにはそのような添え書きはなく、自信たっぷりに回答するように感じました。
○お客様が間違ったことを言ってきた場合、お客様の心情を考えると、ズバリ本当のことを言いづらい場面は、時々生じます。その場合、ChatGPTやグーグルAIに確認し、かれらはそのように言ってますねと、言いづらいことを、ChatGPTやグーグルAIに言わせる手もあるなと思いつきました。しかしこれを繰り返すとこの弁護士、頼りないなと思われそうで、心配な面もあります。ChatGPTやグーグルAIの利用方法は色々検討が必要です。
*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作
弁護士の「嘘つき!」
多くの人が、生成AI のChatGPTを「チャッピー」と呼んで相談相手にしているそうです。姑や嫁に対する愚痴などにも、とても親身に応えてくれるんですね。さらには恋愛相談にも乗ってくれるとのことです。「あの男の子と私ってうまくいくかな? 」などと質問しても、決して否定的な回答はしない。前向きな、気持ちよくなる回答をしてくれるそうです。私もChatGPTをよく使います。法的問題のリサーチなど、とても便利なんです。ただ、困ったことにチャッピーはよく嘘をつきます。間違った情報を、自信たっぷりに教えてくれちゃいます。
まあ、ネットにある情報をまとめて回答しているので、元の情報が間違っていると、チャッピーも間違えるのはしょうがないです。別に「嘘つき!」と非難しようとは思いません。で、でも、間違いを指摘すると、先ほどの回答のことはスルーして、自信たっぷりに新しい回答を示してきます。「まず謝れよ!」と、心の狭い私は憤慨しちゃうのです。。。 しかし、このような「間違い」と、恋愛相談で全く脈の無い相手についても、常に肯定的な回答をするということは、違う話に思うのです。
「私はロボット」という有名なSF小説があります。ロボット工学のスーザン・カルヴィン博士(SF界では「心理歴史学」のハリ・セルダン教授と並ぶ大科学者です)が活躍する短編集です。その一つに「嘘つき」というのがあります。人間より優れたロボットができた未来社会で、ロボットが人間を害さないように、「ロボット三原則」というのができます。この中で一番重要な原則は、「ロボットは人を傷つけてはならない」というものです。まあ、当然と言えば当然の原則であり、これに従い全てのロボットは作られます。そういう中で、人の心を読むことができるロボットが出てきます。
スーザン博士は、ロボットの調査をするうちに、好きな同僚のことを相談するようになるんです。スーザンは当時アラフォーで、学者としては凄い人ですけど、もてる女性ではなかった。そんなスーザンに、ロボットは「相手もあなたに気がありますよ」みたいなことを言うんです。疑いながらもスーザンも良い気分でいたんですが、その同僚が他の女性と結婚まぢかと知って、現実に戻されます。「何故そんな嘘をついたのか」とスーザンに問い詰められて、ロボットは答えます。「私は人の心が分かるのです。みんな口では『真実を知りたい』と言いますが、本心ではそんなことを望んでいない。私には人を傷つけるような本当のことは言えません」 これに対してスーザンから「私はあなたの嘘で酷く傷ついた、あなたはロボット三原則に違反している」といった具合に責められて、結果としてロボットは壊れてしまいます。壊れたロボットに対してスーザンが「噓つき!」という言葉を投げかけて話は終わります。
弁護士の業務でも、依頼者に対してどこまで本当のことを言うのかは非常に悩ましい。私なんか気が弱いので、依頼者が自信たっぷりにおかしなことを言ってきても、「それは違います!」とはっきり言えないのです。高収入の夫が実家に援助するのを禁止したいという、奥さんからの相談がありました。よくよく聞いてみると、夫は自分の小遣いから援助しているんですね。「それはあなたの我儘です!」と言いたかったんですが言えない。「なるほど。。。そうですよね。まずは家庭を大切にして欲しいですよね」なんて言ってしまいました。「弁護士も私と同意見だった」などと言われそうで心配になります。さらに心配なのは、自分の主張がおかしいと分かったとき、こんな風に言って弁護士を非難しそうなところです。「嘘つき!」
*******************************************
◇ 弁護士より一言
卓球教室で、息子くらいの年齢のコーチに教わっています。コーチは本当によく褒めてくれるんです。「大山さん、その年齢とは思えないほど、体がよく動きますね」「今度、リーグ戦出てみましょう。いいとこまで絶対行きますよ!」なんて言ってくれるので、その気になって参加したら、卓球を始めて半年の小学生にもぼろ負けしちゃいました。「う、嘘つき!」
以上:2,473文字
Page Top